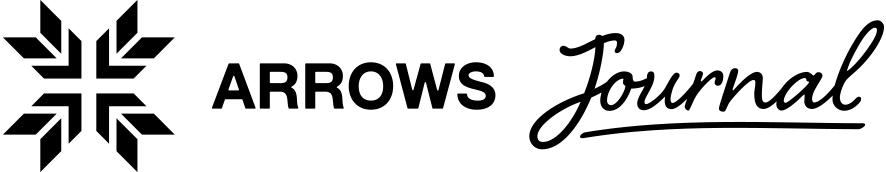
JOURNAL #2412023.08.10更新日:2025.02.14
ライター:大久保 資宏(毎日新聞記者)
「防災対策をしっかりとやって負傷者を減らさないことには話にならない」
そう語る日本医科大の布施明教授の研究チームは、負傷者をどの程度抑制すれば、病院は対応できるのかについてもシミュレーション分析をしています。その結果、首都直下地震の場合、負傷者が5割を超えると医療崩壊を招きますが、4割にまで減ると十分に対応でき、未治療死はほぼゼロになることがわかったのです。
負傷者を減らすのに効果的なのは、やはり建物の耐震化や家具類の転倒防止策です。内閣府による被害軽減に向けた防災対策も、建物の耐震性と家具等の転倒・落下防止対策の強化を挙げ、津波には自主的かつ迅速な避難、火災には感震ブレーカー(震度5以上の揺れで自動的にブレーカーを遮断する機器)の設置促進が有効としています。

これらの防災対策は、国が行った調査でも、耐震化率が100%になれば、死者は首都直下地震で86%減、南海トラフ巨大地震でも80%減に。家具などの転倒・落下防止対策の強化によって首都直下地震、南海トラフ巨大地震の死者はともに63~64%減。火災も、感電ブレーカーの設置促進で南海トラフ巨大地震の死者は55%減になるとしています。
出典:中央防災会議「首都直下地震の被害想定と対策について」(2013年)、内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定について」(2019年)
ところで、未治療死が災害関連死の一部であることを考えると、関連死の原因や背景を明らかにし、問題を解消していくことも重要です。病院が逼迫する一つの要因と思われるからです。

東日本大震災における災害関連死は3789人(2022年6月現在、復興庁調べ)ですが、復興庁の報告書によりますと、原因の過半数は避難所関連です。「避難所等における生活の肉体・精神的疲労」(33%)「避難所等への移動中の肉体・精神的疲労」(21%)とあり、「病院の機能停止(転院を含む)による既往症の増悪」(15%)「地震・津波のストレスによる肉体・精神的負担」(8%)「病院の機能停止による初期治療の遅れ」(5%)「原発事故による肉体・精神的疲労」(2%)などと続きます。
災害関連死の原因についての市町村からの報告事例として、避難所関連では「冷たい床の上に薄い毛布1枚」「出入口付近にいたため足元のホコリにより不衛生な環境」「寒いため布団の中にいることが多く、体も動かなくなり食事も水分も取らなくなった」「配給はされたが、普段から柔らかいものを飲食していたので飲食できる量が少なかった」「顆粒状の薬しか飲めないのに粒状の薬を処方されていた」「断水でトイレを心配し水分を控えた」「狭いスペースに詰め込まれ、精神・体力的に疲労困憊の状態」「不眠行動、せん妄の症状が出始め、精神薬を投与するが改善無し」「胃ろう、寝たきりの人が、バスで8時間かけて避難」などとあります。
その他、病院の機能停止で「病院職員がほとんど緊急避難してしまい、適切な治療を受けられない状況に陥った」。原発事故では「医師・看護師等が患者を放置し避難し、妻が1週間近く放置され精神的に著しいショックを受けた」などです。
出典:復興庁「東日本大震災における震災関連死に関する報告」(2012年)
避難所などでの生活環境や健康・衛生管理の問題は、阪神大震災でも指摘されていました。にもかかわらず、東日本大震災や熊本地震(2016年)でも繰り返され、大勢の人が亡くなっています。この他、避難所に行くことができなかったり、行っても過密状態で車椅子では往来がむつかしかったりして、倒壊しかけた自宅に戻らざるを得なかった障害者もいます。このような非常時における過酷な状況についても議論を重ね、早急に解消する必要があります。
また、医療資源が圧倒的に不足する事態に「救命救急士に輸血などの医療行為の権限を一部付与すべきだ」と言うのは、神戸学院大の中田敬司教授(災害医療)です。「一刻を争う事態の中、すべてに医師の許可を必要とすべきでない」と主張。布施教授も「日本で医療に携わるからには『災害医療』を必須にし、何かあればすぐに第一線で治療できる教育水準に持っていかねばならない」と指摘します。

未治療死を減らす最前線にいる医療者側の安全も無視できません。
中田教授によりますと、熊本地震では建物がいつ倒壊するかわからないような状況下、「DMATがどこまでリスクを負って治療を続けるかという課題が残った」と言います。「現地の医療従事者が懸命に活動する中、中に入れないというのは同じ医療者としてどうか。消防や警察と同列とはいかないが、現地の医療従事者と同じくらいのリスクは負うべきだ」といった意見が多く、中田教授は「明確な線引きはなく、議論を深める必要がある」と話しています。
未治療死を減らす取り組みが各地で行われており、一部を紹介します。まずは、「医療の早期介入」と「迅速な広域搬送」のいずれも可能にする「災害医療支援船」と「野外病院」(フィールドホスピタル)です。

陸路が寸断された被災地や離島への医療支援には海路を使う船舶が有効ですが、建造費や維持費などがネックで導入の機運がなかなか高まりませんでした。ところが、東日本大震災をきっかけに国による有識者検討会や超党派の議員連盟が発足。2021年、「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律」が成立しています。
同法施行を前に、NPO法人ピースウィンズ・ジャパン(PWJ、広島県神石高原町)は災害医療支援船「Power of Change」(3453トン、全長68メートル、幅17.4メートル)を完成させ、就役披露式が7月2日、母港となる愛媛県今治市宮窪町の早川港でありました。医療が主目的の船は国内初で、最大49人分の患者用の個室や備蓄品が用意され、後方にはヘリパッドも設置。ドクターヘリによる搬送も可能です。
民間企業などからの出資で、パナマ船籍の調査船を修繕しました。平時も船員が待機し、発災時に同法人や提携するDMAT等の医師や看護師らが乗り込みます。一般家庭100世帯以上の電源がまかなえるほか、生活用水500トンの生活用水が常時あり、傷病者や被災者の受け入れや診療、物資・燃料の補給、支援者の休息などに使われ、約2カ月間の生活が可能です。
PWJの稲葉基髙医師は「一人でも多くの人を救う戦略の一つ。支援者も朝から何も食べていない、何も飲んでいないという状況ではパフォーマンスがすごく落ちる。平常時に近いコンディションで支援できるのはありがたい」と話します。

災害時に負傷者を野外で診療する移動式救護施設が野外病院です。戦時の野戦病院のように、校庭や広場などに大型テントを張ってさまざまな医療活動を展開します。
被災地でよく見かけるのが陸上自衛隊です。コンテナユニットをトラックに積んで移動し、校庭などへの大型テント内で診療所として負傷者や急病人らを受け入れる想定で手術ユニットもあります。入浴セットなどもあり、避難者らの生活をサポートします。
日本赤十字はdERU(国内型緊急対応ユニット)を整備しています。トラックで移動できる仮設診療所として医薬品や医療資機材のほか、レントゲン室や手術室、ICU、要員の宿泊棟などもあります。
医師や看護師、助産師、薬剤師、事務職員ら14人が基本要員で、1日150人程度の軽症・中等症程度の傷病者に3日間にわたって治療ができ、状況に応じて延長します。
2020年にスタートしたのが民間初となる、ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)の野外病院です。ヘリコプターが使える患者搬送機能を有する施設で、診療所レベルの問診や診察、処置をします。
テントの中には、救急室やレントゲン室、薬局、処置室(病床)、血液検査室、隔離室、遺体安置所などがあり、現在、約50の自治体や病院と協定を結んでいます。
稲葉医師は「公的機関ができないことをやるのが民間の強み。我々の活動によって被災地内の病院の負担を軽減することで1人でも多くの未治療死を減らしたい」と話しています。
また、国の被害想定に危機感を募らせ独自に対策に乗り出したり、住民を巻き込んだユニークな取り組みを行ったりしている自治体もあります。
南海トラフ巨大地震の被害想定で最大の死者数が見込まれる静岡県では10年計画のアクションプログラムが3月に終了し、新たなプログラムに移行しています。
同県によりますと、この10年間に住宅の耐震化(89.3%達成)や災害拠点病院などの公立建築物の耐震化(100%達成)、防潮堤の整備、家具の転倒防止対策のほか、救急体制(救命救急士や消防団員の確保)や災害時の医療救護体制(災害薬事コーディネーターの養成)の強化などで当初想定の死者約10万5000人から約8割減の約2万2000人になったとしています。
家具転倒・落下による死者数が最多とされる愛知県では、家具固定の普及を目的に2015年度から「家具固定推進員」派遣制度を導入しています。推進員になるには県が行う研修を修了する必要があります。
推進員(今年2月現在で166人)は地域の講習会やイベント、防災訓練などに出向いて家具固定器具の取付実演や啓発活動を行っています。
死者数が3番目に多いとされる高知県は2013年から独自に「地域災害支援ナース」制度を実施しています。津波や土砂崩れなどで地域が孤立し、支援が遅れることを想定した取り組みです。
災害が起きたら、登録した看護師(昨年3月現在で568人)は勤務先とは関係なく、最寄りの病院や避難所に入ることを取り決めています。看護職の資格があれば年齢は問いません。
海底地震津波観測網を活用したシステムを導入しているのが、和歌山県と三重県です。沿岸地域では津波の襲来からいかに早く避難するかが重要です。
同システムは津波警報と異なり、沖合で観測した津波の高さなどをもとに浸水範囲の予想を刻々と更新する「実況中継」が特徴で、地震が起これば、住民のスマートフォンなどにエリアメールで避難を呼びかけます。
WRITER
ライター:
大久保 資宏(毎日新聞記者)
毎日新聞社では主に社会部や報道部で事件や災害、調査報道を担当。雲仙・普賢岳災害(1990~95年)と阪神大震災(1995年)の発生時は記者、東日本大震災(2011年)は前線本部デスク、熊本地震(2016年)は支局長として、それぞれ現地で取材した。
SUPPORT
ご支援のお願い
支援が必要な人々のために
できること
私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。
一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。