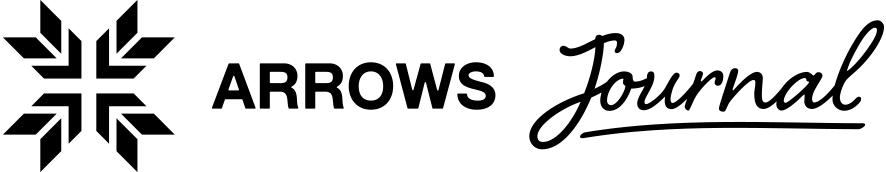
JOURNAL #2482023.09.06更新日:2024.11.22
ライター:大久保 資宏(毎日新聞記者)

大規模災害が起きると、病院や診療所の多くは機能不全に陥ります。発生直後、被災地に駆けつけて仮設の医療施設を設営し負傷者らの治療にあたるのが野外病院(フィールドホスピタル)です。国の中央防災会議は2014年3月、「大規模地震防災・減災対策大綱」を策定し、自治体などに野外病院の開設を検討するよう求めました。あれからやがて10年。設営に向けた動きは進んでいるのでしょうか。野外病院の現状や役割、課題について考えます。

野外病院は、戦時の野戦病院のように校庭や公園などに主に大型テントを張って医療活動を展開します。WHO(世界保健機関)のEMT(緊急医療チーム)は、野外病院を規模に応じて以下の3つに分類しています。
被災地でよく見かけるのがテント型で、救急車やバス、列車などを転用する自走可能型、トラックや列車、航空機での搬送が可能なコンテナ型などもあります。
野外病院といえば、倒壊した家屋の瓦礫の下から救出された負傷者を治療するイメージがあります。今年2月に発生したトルコ・シリア地震の被災地に日本の国際緊急援助隊(JDR)が開設した野外病院では、病院から避難してきた入院患者らの対応に追われたといいます。このように野外病院には、災害による負傷者や、全半壊した病院からの入院患者、避難所で体調不良を訴える傷病者など、さまざまな人たちへの対応が求められます。
現在、国内で野外病院を運用しているのは主に自衛隊や日本赤十字、JDR、NPO法人ピースウィンズ・ジャパンなどです。日ごろから車両に医療機器などを積んでおり、災害が発生すると、直ちに現地入りしてテントを設営、医師や看護師らが治療にあたることになっています。開設場所としては、負傷者が多くて医療が手薄になっている所や、避難所や学校などの公共施設、ヘリポートのある搬送基地などが候補になります。
ところで、災害時に地域の中心的な医療を担うとされる災害拠点病院ですが、全体の3~4割が水没するリスクがあることが、さまざまな調査で明らかになっています。

例えば、神戸学院大の前林清和教授らの研究チームの調査によりますと、南海トラフ巨大地震の死者数が5000人以上と想定される11府県のうち海岸線を持つ市町にある災害拠点病院(119施設)の37%が浸水によって診療機能が麻痺する可能性が高いとしています。読売新聞も、全国調査(2021年)で、全災害拠点病院(759施設)の41%が浸水する恐れがあり、床上以上の浸水が見込まれる病院へのアンケート調査では5割以上が「病院機能を維持できない」と答えたと報じています。
このため「安全な場所に移るべきだ」という意見もあります。ただ、全国公私病院連盟の病院運営実態調査(2021年)の結果、全国593病院の77%が赤字で、移転やそれに伴う改築は容易ではありません。何より、移ることで医者のいない無医地区(市町村)がますます増えて地域医療が崩壊しかねません。住民の健康を維持できなくなるので、早計に移転するのはやはり問題です。
当該病院が浸水域にとどまる以上、建物の補強や、止水板・排水ポンプの設置、医療機器や発電機を上階に移すとともに、補完機能を備える野外病院も視野に入れた災害医療対策を講じる必要があります。

「国、地方公共団体、関係機関は、被災地における医療機能を確保するため、被災地外から移動式救護施設を搬入し、野外病院を開設するための体制について検討する」
2014年に中央防災会議がまとめた「大規模地震防災・減災対策大綱」の野外病院に関する一節です。対策大綱は、予防から復旧・復興対策までのマスタープランで、これまで5つありました。
東海地震、東南海・南海地震▽首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、中部圏・近畿圏直下地震のそれぞれに大綱が策定され、これらに、首都直下地震対策検討ワーキンググループと南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ双方の最終報告で明らかになった検討課題などを合わせて一本化したのが「大規模地震防災・減災対策大綱」です。
「野外病院」に初めて踏み込んだ対策大綱が取りまとめられて間もなく10年になります。目立った動きがないことに、南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループの主査を務めた河田惠昭・関西大学社会安全研究センター長は「中央防災会議で承認されて即動くという単純なものではない。医療関係者、つまり厚生労働省など関係省庁の同意がいるが、内閣府防災はマネジメントする部局ではない」と言います。
ただ、その一方で、病院船に関する議論や、国土強靱化基本計画などに伴い浮上してきたのが「医療コンテナ」です。

元国土強靱化担当大臣の古屋圭司衆院議員を会長とする「コンテナ利用の緊急時医療施設議員連盟」が2017年に設立され、翌18年に発足したのが業界団体による「医療コンテナ推進協議会」です。同協議会のホームページには、議員連盟と協働して法整備や関係省庁への調整を目指すとありますが、呼応するかのように各省庁は自治体などに医療コンテナの活用を働きかけるなどさまざまな動きをしています。
新型コロナ感染症も拍車をかけました。病院などへの医療コンテナ導入に補正予算(新型コロナ感染症緊急包括支援交付金)が組まれ、発熱外来の院外施設やPCR検査室として利用する医療施設が相次いだのです。
厚生労働省は2021年、医療コンテナに関する調査で、以下のように分析しています。
1. テントに比べ、清潔性、堅牢性、耐候性に優れ、水や電気の供給設備の配備やCT等の大型の医療機器を搭載できる
2. プレハブに比べ、医療機器を搭載した状態での運搬が可能で、災害時に被災地に運搬し医療提供が可能等、災害時の活用における利点がある
同省は、この調査結果を踏まえ、22年の国土強靱化年次計画に「災害医療等の対策として医療コンテナの普及・導入促進について検討する」と明記。24年度からの第8次医療計画には、当初なかった「医療コンテナの災害時の活用」が加わり、自治体に求められる事項として「災害時の医療提供体制を維持するために医療コンテナ等を活用し、例えば、仮設診療所の設置や被災した病院施設の補完等を行う」としています。
内閣府も同様に2021年の「経済財政運営と改革の基本方針」で「医療コンテナの活用を通じた医療体制の強化」を強調しています。そして今年7月、国土強靱化基本計画が閣議決定されました。「総合的な防災拠点施設にて医療コンテナをはじめとする診療ユニットについて平時活用を含め検討する」とあり、本格導入に舵を切ったといえます。
野外病院の行方が一転したことに、圧力団体に政治家も加わって省庁を巻き込んでいるのではと勘ぐる向きもあります。ただ、災害医療対策は確実に前進しつつあり、医療現場から歓迎する声も少なくありません。

ピースウィンズ・ジャパンのプロジェクトリーダーである稲葉基高医師は「野外病院の議論が医療コンテナに移ってきたのは正しい感覚。医療コンテナも野外病院の一つの形だし、私としてはテントだろうが、コンテナだろうが、ちゃんとしたものができればいい。テントの良さ、医療コンテナの良さ、それぞれあるので、あまりこだわらずに柔軟にやるべきだ」と話します。
ところで、野外病院の運用にはいかなる課題があるのでしょうか。
災害後の混乱のさなかに設営される野外病院では、限られた設備のうえ、診療現場は負傷者らであふれかえります。そのような状況下、現場の医療資器材を用いての治療、時に輸血や検査をしますから、相当な経験や知識、技術のほか、職種や専門性を超えた医療支援も求められます。自衛隊や日本赤十字、ピースウィンズ・ジャパンなどは、そのような人材を確保しつつ、研修や訓練を行っています。

手間がかかるのが維持管理です。
日本赤十字は、普段から医療機器や医薬品などをコンテナ内で管理しています。ただ、ロジスティックセンター(災害専用の倉庫)には医療消耗品などが5万点超あり、中出雅浩・大阪赤十字病院国際医療救援部長は「薬には有効期限、ガーゼ類には滅菌・減菌期限がある。定期的に入れ替えているが、医療機器のメンテナンスもしなくてはならない。コンテナも同じ。野外病院はいつでも出動できる体制にしており、24時間、これらを維持管理するのはすごく大変だ」と言います。
野外病院を保有している関係機関の取り組みを紹介します。
自衛隊は、ライフラインが整備されていない環境下でも最新鋭の機動力を使った医療行為が可能で、都道府県などからの要請を受けて出動します。

野外病院としての治療・診療対象は隊員がメインですが、東日本大震災では、陸上自衛隊の機動衛生ユニットが自衛隊仙台病院の隣接地に野外病院(応急救護所)を開設し被災住民の治療にあたりました。同ユニットは医療行為を行いながらの長距離輸送も可能で、診療や健康相談の件数は2万5000件以上にのぼったということです。
陸上自衛隊は1988年に野外手術ユニットを導入しており、外科手術や応急治療が可能です。同ユニットの目的は、負傷した隊員の救命率の向上ですが、状況次第で災害時にも出動し、負傷した被災住民も診ることになっています。
大型トラックに搭載された手術室(治療室)では一日10~15人程度、開胸や開腹、開頭などの処置ができるとしています。
また、航空自衛隊は救護班の派遣や各基地における医療搬送拠点の運営支援・人員輸送など、海上自衛隊は陸から入れない孤立した地域からの艦船への負傷者収容や救護班への派遣などを、それぞれ行います。
参照:防衛省ホームページ、月刊MAMOR(扶桑社、2015年10月号)、国立病院機構災害医療センター「大規模地震時における既存艦船を活用した医療活動に係る実証訓練支援及び調査業務実績報告書」(2018年3月)
国際赤十字は1990年代に自然災害に即応できるよう、医療資器材をまとめてユニットにする「Emergency Response Unit」(ERU)構想を打ち出しました。日本赤十字はクリニック型 ERU を国内に1基、ドバイに1基を保有しています。国内向けには、自己完結型の医療チームを即応させるために、厚生労働省と共同で、昇降式コンテナにすべての資機材を積み込んだトラッククリニック型ERU(dERU)を完成させ、現在20基を太平洋側を中心に各支部に配備しています。
陸路の車両による移動で、設営には約60~90分。要員は、医師2人、看護師長2人、看護師4人、助産師1人、薬剤師1人、事務4人の14人です。平時は、公的イベントや防災イベントなどへの出展で、災害時には被災地での救護所や巡回診療等の活動拠点、後方搬送における傷病者の一時収容、被災医療施設の支援を行います。
仮設救護所のため規模はクリニックレベルですが、比較的コンパクトで車両と一体に整備されるうえに普通運転免許で運転できるため機動にも優れています。
また、病院レベルの野外病院が、大阪赤十字病院に常駐している「ホスピタル dERU」(災害対応フィールドホスピタル)です。マイクロバスの中にレントゲン設備や手術ユニット、病棟テント、ICU(集中治療室)などがあり、電気や水、食料、宿泊施設、通信インフラなどが途絶えても医療を継続できるのが特徴です。
要員は医師5~6人、看護師9~11人、助産師1人、 薬剤師2人、放射線技師2人、臨床検査技師1人、理学療法士1人、臨床心理士1人、管理要員12人の30~40人体制です。
参照:日本赤十字社ホームページ、大阪赤十字病院ホームページ、国立病院機構災害医療センター「大規模地震時における既存艦船を活用した医療活動に係る実証訓練支援及び調査業務実績報告書」(2018年3月)
2020年にスタートしたピースウィンズ・ジャパン(PWJ)の野外病院は、ヘリコプターによる患者搬送機能を有する民間初の取り組みです。訓練を重ねるなどいつでも出動できる状態にあり、診療所レベルの問診や診察、処置をします。

プロジェクトリーダーでもあるPWJの稲葉基高医師は、災害支援医療チーム(DMAT)の一員として東日本大震災の被災地に派遣されるなど、数多くの災害現場で支援活動を行っています。稲葉医師のこれまでの経験も活かしながら整備した野外病院といえます。
稲葉医師によりますと、最大の目的は「病院にたどりつくことができない人に医療を届けること」です。傷病者への治療だけでなく、状況に応じて、患者をヘリコプターや車で適切な病院に運んだり、エッセンシャルドラッグ(欠くことのできない医薬品)が無くて死のリスクが高まっている人たちをケアしたりもします。

展開する野外病院では、テントの中に救急室やレントゲン室、薬局、処置室(病床)、血液検査室、隔離室、遺体安置所などを配置します。要員は、医師が5人のほか、看護師やロジスティックなどの管理系も含め約30人。現在、約50の自治体や病院と協定を締結しています。
稲葉医師は「日本赤十字や自衛隊にとってむつかしいのは、一つの組織での運営するという点。DMATが自衛隊や日赤のフィールドで治療することはあまりない。公的機関ができないことをやるのが民間の強みだと考えている。我々の活動によって被災地内の病院の負担を少しでも軽くし、1人でも多くの未治療死を減らしたい」と話しています。
参照リンク
・空飛ぶ捜索医療団ARROWSホームページ
・国立病院機構災害医療センター「大規模地震時における既存艦船を活用した医療活動に係る実証訓練支援及び調査業務実績報告書」(2018年3月)
WRITER
ライター:
大久保 資宏(毎日新聞記者)
毎日新聞社では主に社会部や報道部で事件や災害、調査報道を担当。雲仙・普賢岳災害(1990~95年)と阪神大震災(1995年)の発生時は記者、東日本大震災(2011年)は前線本部デスク、熊本地震(2016年)は支局長として、それぞれ現地で取材した。
SUPPORT
ご支援のお願い
支援が必要な人々のために
できること
私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。
一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。