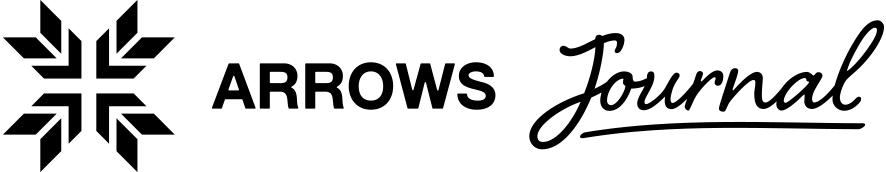
JOURNAL #2862023.12.31更新日:2024.02.14
ライター:大久保 資宏(毎日新聞記者)

大規模災害が起きると、被災地では行政やボランティアらによるさまざまな支援が行われます。炊き出しや救援物資の支給、がれきの撤去……。このような支援は、古くは古代にまでさかのぼります。未曽有の災害に見舞われた人たちは、これまでいかなる援助を受け、どのようにして日常を取り戻したのでしょうか。災害支援の変遷とともに、その在り方や課題について考えます。
そもそも、災害支援とは何でしょうか。
大規模災害の発生直後、多くは着の身着のまま近くの学校や公民館などに避難します。行政は対策本部を設置しボランティアらとおにぎりを振る舞ったり、水やカップ麺、衣料を提供したり、被災家屋の泥出し・清掃をしたり。警察や消防、自衛隊は倒壊家屋からの救出や行方不明者の捜索、医師や看護師らは負傷者の治療にあたります。しばらくすると、税の減免や貸付金、寄付金・補助金支給など生活再建に向けたさまざまな施策がはかられます。

これらの支援は、災害の規模や時代背景、発生場所(都市部か山間部か沿岸部か)・時期・時間、被災者の特性(年齢や性別、障害の有無、国籍、家族構成、就労状況、健康状態など)によって、その内容は大きく異なります。「災害は進化する」と言うように、時代とともに町並みは変わり、災害による被害も、支援も変化します。
支援期間は、災害の発生直後から生活再建に至るまでで、東日本大震災(2011年)のように被害規模が大きいと5~10年、場合によってはそれ以上かかり、継続がむつかしいケースも出てきます。
災害支援を巡っては、お上(官)主導の時代から民間頼みの相互扶助、やがて新聞の義援金募集で多額の支援金が全国から寄せられるようになり、相互扶助の形が一変しました。近年、ボランティアや、空飛ぶ捜索医療団”ARROWS”のようなNPO法人が、行政の手の届かないところにも細かな支援を続けています。
以下は、過去の大きな災害と国による対策をまとめた年表です。

今回はこの中から、時代別に主要な災害の概要や支援内容をみていきます。
律令国家では、天が人間(為政者)を罰するために災害を起こすという「天譴論」(てんけんろん)に基づき、政府による食料や衣料の支給「賑給」(しんごう)が行われました。戦乱や干ばつ、大雨などによる飢饉が頻発したことから、大化の改新(645年)の際は穀物を備蓄する義倉を導入し、生活困窮者に配給しています。
政府は、以下5つを指示。
その後の地震などでも、同様の支援をしており、上記の内容を「地震対策パッケージ」としてマニュアル化していたとみられています。
朝廷や幕府は、寺社に災厄駆除や国家安穏を祈願させ、京都や鎌倉などでは寺院や僧侶が飢疫民に食料を支給する施行(せぎょう)を行っています。室町時代には、飢疫や年貢の過重などによる土一揆を恐れて金貸しなどが施行の資金を寄付しています。
この頃には地震だけでなく、火災や飢饉への対策も重視されるようになりました。
江戸幕府は一揆を恐れ、食料や種籾(たねもみ)料、農具料として米金の支給や貸付をし、江戸の大火(1657年)を機に食料提供や家賃免除、長期無利子の「拝借金」制度が定着。
西日本を中心に起きた飢饉(1681~83年)では、寺院や僧による施行や、商人による寄進(有力者や寺社に金品などを寄付すること)をしています。とりわけ享保の飢饉(1732年)の際は、相互の助け合いの触れを出したり、協力した人たちの名前と寄付金の額を本に仕立て「仁風一覧」として出版したりしています。

小田原藩は幕府から災害復旧の貸付金1万5000両を得て、
①箱根口に大釜5つを据えて粥施行(一日米俵10俵を7日間にわたって炊き出し)
②伊豆領に緊急食糧600俵を貸し付け
など、7項目の対策を実施。


絵図のように火災を伴う大災害となり、奉行所が炊き出しなど、以下9項目の支援策を決定し実行。
地震から3日後には、浅草など5カ所に一時避難所「お救い小屋」を設け被災者約2700人を収容したり、深川永代寺など5カ所で1週間、延べ20万2400人分の握り飯を提供。「其の日稼ぎの者」とされる男性(15~60歳)には白米5升、女性および15歳以下、61歳以上には白米3升を、計38万1200人に支給するなど、複数の支援施策が実施されました。
また奉行所以外でも、富商らによる炊き出しや、金銭や味噌、茶、そば、沢庵、梅干し、サツマイモ、干魚、むしろ、手ぬぐい、漬物、生活必需品などの配給が実施されました。
明治時代には、国家の予算編成で災害対応を行う形が整備されていきました。備荒儲畜金法(1880年)に基づく救済金の支給や天皇・皇后による恩賜金制度も始まったほか、個人による義援金の拠出も多額になりました。ただ、地域社会が有する自力救済システムが脆弱化したとの指摘もあります。
現在も活動を続ける日本赤十字社が、初の災害援護活動を展開。

日本赤十字社の前身である博愛社は1877年の西南戦争時、傷病者を敵味方の別なく救護することを目的に設立され、’86年のジュネーブ条約の加盟に伴い翌’87年に日本赤十字と改称。国内外を問わず、救護活動を行っています。その役割は災害救助法(1947年)、災害対策基本法(1961年)で、政府の指揮監督下にあることなどを規定。災害発生時には、災害対策本部の要請で救護活動を行うことになっています。

国は、被害状況に応じて、災害弔慰金や災害障害見舞金、被災者生活再建支援、災害救護資金などを制度化。民間レベルでは、新聞のほかテレビやインターネット、SNSなどメディアが多様化し義援金システムがより拡大し、多数のボランティアやNPO法人などが積極的に活動しています。
とりわけ近年のNPO法人や災害NGOの特徴は専門性にあるともいえます。福祉施設を中心に物資配付や施設の修繕などに取り組む「難民を助ける会」(本部・東京)や、保有ヘリなどで医師や医療スタッフを直接送り込んで救命救急にあたったり、ペット支援も行ったりする「ピースウィンズ・ジャパン」(本部・広島県神石高原町)、震災孤児の進学をサポートする「あしなが育英会」(本部・東京)など、行政側の対応の遅れや漏れ、むらをなくす役割も果たしています。

また、企業による支援も相次ぎました。一部を列挙します。
また、物資支援やボランティア派遣のほか、企業からNPO法人に資金を寄付することで、NPOの活動を支援する形態も一般化しつつあります。
以上、各時代における支援状況を紹介しましたが、首都直下地震や南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、課題もあります。
よく指摘されるのが、ボランティアらの受け入れ体制の不備や、障害者(災害時の死亡率は全体の2~4倍)や高齢者らを含む被災者ニーズに立った視点の欠如です。また、行政、ボランティア、NPOの3者連携や支援者間の調整を行う「被災者支援コーディネーション」の基盤整備に向けた議論が活発ですが、凄惨な状況を目撃したことでの惨事ストレス(心的外傷ストレス反応)を訴える消防や警察、医療、報道関係者らへの支援など課題は山積しています。
今後、いかなる支援が求められるのでしょうか。
災害史研究の第一人者、北原糸子さんは「食料供給ももちろん大事」としたうえで「それだけに終わらない支援。たとえば、関東大震災の時の『関西村』みたいに社会への問いかけとなるような、何を実現したいのか伝わるような、新たな形を打ち出すような、そんな支援を期待したい」と話します。
関西村とは、関東大震災後、関西などの府県の支援で横浜市内に建設されたバラック住宅で、約1年半、被災者約2000人を収容しました。幅約450㍍、奥行き約130㍍の建物には病院や公設市場、食堂、小学校、警察署、消防署も備えるなど、都市機能を喪失した地域への、震災とは無関係の自治体の相互連携による画期的な支援でした。

関東地方震災救援誌などによりますと、震災から4日後の1923年9月5日、大阪が中心となって話し合い、2府11県の参加が決定。府県連合は東京に300棟、横浜に200棟を建設し、うち52棟が関西村で、棟ごとに「石川通り」など支援した府県名が書かれた看板を設置しました。内部には間仕切りがあり、各世帯の部屋は約4~6畳。病院は最大451人の受け入れが可能で、図書館の仮施設もあったとのことです。
| ※参考 北原糸子「日本震災史」ちくま新書 北原糸子「磐梯山噴火~災異から災害の科学へ~」吉川弘文館 中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会編「災害史に学ぶ」 「津波、噴火……日本列島 地震の2000年史」朝日新聞出版 弘胤佑「奈良・平安時代における災害と国家」 川原由佳里、吉川龍子、川島みどり「日本赤十字社の災害救護関連規則の歴史」日本看護歴史学会誌第20号 |
WRITER
ライター:
大久保 資宏(毎日新聞記者)
毎日新聞社では主に社会部や報道部で事件や災害、調査報道を担当。雲仙・普賢岳災害(1990~95年)と阪神大震災(1995年)の発生時は記者、東日本大震災(2011年)は前線本部デスク、熊本地震(2016年)は支局長として、それぞれ現地で取材した。
SUPPORT
ご支援のお願い
支援が必要な人々のために
できること
私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。
一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。