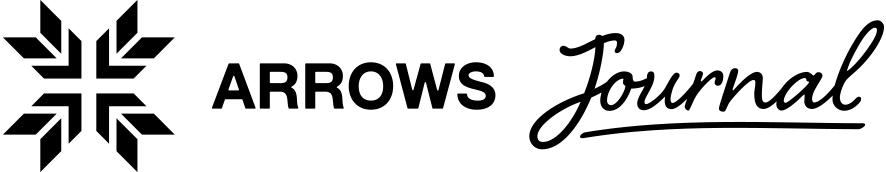
JOURNAL #3862025.01.02更新日:2025.02.07
ライター:若月 澪子

2024年元日に奥能登地方を襲った「令和6年能登半島地震」。この地震発生時に、どこよりも早く現地の医療支援に駆け付けたのが、NPO団体ピースウィンズ・ジャパンが運営する災害医療支援チーム「空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”」である。
その代表を勤めているのが空飛ぶ捜索医療団のプロジェクトリーダーとして20人もの医療、救護、被災地支援のプロを束ねる、医師の稲葉基高。日本海に手を伸ばす半島の指先の珠洲市で、彼らの能登半島地震の支援活動はスタートした。地震発生から1年が経った今、稲葉の目を通してあらためて当時の記憶と記録を振り返るドキュメント連載・第2回――

稲葉がNGOピースウィンズの専属医師になったのは、5年前のことだ。
それまで稲葉は岡山済生会総合病院の救急センターで働く勤務医だった。このまま続ければそのうち救命救急センター長……そんな先のこともチラチラと見えはじめた頃である。
そもそも「NGOの専属医師」というポジションは、医師の世界ではほとんど前例がない。
「なぜ病院を辞めるんだ、勤務医であっても、災害医療に携わることはできる。今これまでのキャリアを捨てるのはもったいない」
稲葉の周囲の医師たちは、こぞって稲葉の「転職」に反対した。
もちろん、稲葉本人もすぐに決断できたわけではない。最初にピースウィンズから誘いを受けたとき、稲葉はあっさりと断っている。
「NGOとして紛争地域の支援をやっているピースウィンズの代表の大西さんが、専属の医師を雇いたいといっている。岡山に稲葉君という元気な子がいるからって、連絡先教えておいたから」
稲葉が、災害支援現場で世話になった「HuMA(災害支援を行うNGO団体)」重鎮の医師から最初にそう言われたのは、2012年の頃だった。多忙を極める医師の世界では「個人情報は安易に教えない」というルールはあまりない。勝手に連絡先を教えられてしまった稲葉は、何のことかわからずにその話を聞いていた。
その後、ピースウィンズの代表である大西の秘書という女性からのメールが二回ほど稲葉の元に届いた。
「NGO?…ちょっとないわ」
稲葉にとってNGOの専属医師というのは、見たこともない未来だった。

しかし、当時の稲葉には、救急医としてさまざまな葛藤が生じていた。
たとえば、救急車で救急救命センターに運ばれてくる患者の多くは、80歳を過ぎた高齢者である。本人が延命を希望しているかどうか不明なことが多く、救急救命医はとりあえず人工呼吸器を入れて延命措置をすることがほとんどだった。
認知症の人の場合だと、点滴を抜かないように手を縛り、「ゴメンね」と言いながら鼻からビューっと痰を吸引し、おばあちゃんが「うええ」と嫌がっても処置をすることもある。これがドラマだったら、正義感あふれる看護師が立ち上がり、「こんなに縛って鼻から管を入れるなんてかわいそうだから、やめてください!」と言うかもしれない。しかし現実はそうならない。
認知症患者の場合、縛りつけなければ点滴を抜かれて徘徊し、転んで骨折する危険もある。病院が訴えられでもしたら、誰が責任とるんだという話になる。本人にとって何がベストな選択なのかを確認できないまま、とにかく処置をする、それが救急医療の現実だった。
「医療は人を幸せにする仕事のはずなのに、実は幸せに繋がっていないのではないか」
情熱を持ってこの仕事に就いたはずの医師や看護師たちは徐々に“医療マシーン”になっていく。マシーンにならなければやっていられなくなるのだ。
稲葉の中で「医療がこれでいいのか」という疑問が募っていた。しかし、何をどう変えればいいのか、稲葉にはわからなかった。
「今のルールを変えるのは難しい。日本の保険財政が破綻して、お金がないと医療が受けられないところまでいかなければ、この状況は変わらないのか。しかし、いくら何でもそれはいびつだ」

そんな稲葉が、ピースウィンズ代表の大西健丞の話に惹きつけられたのは、そのスケールの大きさからだった。
「今の日本の医療に不満があるんやったら、国にルール変えさせたらええやん。何なら、国を通さずにやればええやんか」
そんなことを言う医師は、稲葉の周りには一人もいなかった。
ただ稲葉自身は「尾崎豊」みたいな世界観にちょっと憧れていた。大人に反抗して校舎のガラスを割りまくる若者の姿。学生運動などを経験した世代までは、そういう医師もいたかもしれない。
しかし、稲葉が長崎大学医学部に進学したころ、そんな時代はすでに過去のものになっていた。今の医療現場には、尾崎豊もブラックジャックもいない。「もう少し治療ができれば、患者はハッピーになる。でも診療報酬の点数が決められているから、それ以上のことはしない」
今いるほとんどの医師は、あくまでルール内でベストを尽くすことに全力を注ぐ。ルールからは決してはみ出さない。
状況に違和感を持ちながらも、どうルールを変えたらいいのかわからなかった稲葉は、大西の言葉に、雷に打たれたような衝撃を受けた。
「窓ガラスを割るんやったら、1個ずつ割るなんて面倒なことせんでええやん。ダンプカーでそのままぶっ潰したらええやんか」
稲葉が大西と初めて会ったのは、ピースウィンズの本部がある広島県の神石高原町。標高700mの高原に広がる自然体験型テーマパーク「ティアガルデン」内の、緑の芝生のキャンプ場が一望できるカフェだった。コーヒーをすすりながら飄々と語る大西の言葉に、稲葉は度肝を抜かれた。
「このおっさん、何言っとるんや…」
同時に、稲葉は自分の視野が極めて狭かったことも思い知らされた。

稲葉が普段から感じていた不安と疑問。少子高齢化が日本社会に与える鈍痛は、完治不能な病巣となって社会を蝕んでいくだろう。今の医療の現実を見逃したまま、次の世代にパスしていいのか。
当時、稲葉は30代後半だった。現状に疑問や不満がありつつも、一方で若手には「業界の掟」を伝えていく年代である。
「このままでいいのか」
稲葉は思い切って、この扉を開けることにした。NGOの専属医師になることで、今の疑問が解決できるかはわからない。しかし稲葉にとっては、災害医療も救急医療も同じベクトルにあった。
もし、おばあちゃんが急に苦しくなって救急車で運ばれるのは、小さな家族にとっては災害みたいなものだ。突発的に何かが起こって、みんながパニックになる、日常の幸せだと思っていたものが奪われたときに、誰かに助けて欲しいと思う。
「災害も救急も『助けを必要としている』という点では同じだ。だから自分はそこに行って助ける人になる。誰かを助けて、患者とその家族にハッピーになってもらうのが、自分の仕事だ」
稲葉にとって医療のゴールは「人の幸せ」だということだけは、はっきりしていた。
こうして稲葉はピースウィンズの専属医師として、国内外の被災地で災害医療支援を行うという道に飛び込んだのである。(第1話へ|第3話へつづく)
取材・文=若月 澪子
空飛ぶ捜索医療団”ARROWS” HP:https://arrows.peace-winds.org/
Twitter:https://twitter.com/ARROWS36899898
Facebook:https://www.facebook.com/ARROWS2019
Instagram:https://www.instagram.com/arrows.red2019/
空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”「能登半島地震 緊急支援」の活動記録は以下からご覧いただけます。
WRITER
ライター:
若月 澪子
フリーライター 1975年生まれ。NHKで契約のキャスター、ディレクターとしてローカル放送の制作にあたる。結婚退職後に家事と育児のかたわら、借金苦、就活、中高年の副業に関する取材・執筆を行う。著書に『副業おじさん 傷だらけの俺たちに明日はあるか』(朝日新聞出版)
SUPPORT
ご支援のお願い
支援が必要な人々のために
できること
私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。
一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。