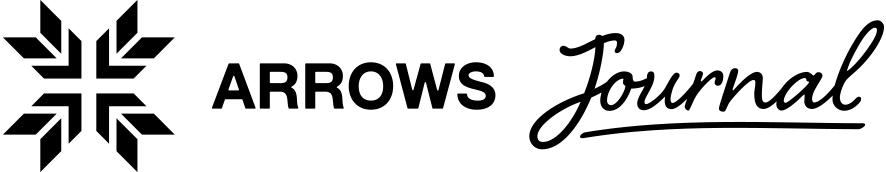
JOURNAL #3922025.01.08更新日:2025.02.07
ライター:若月 澪子

2024年元日に奥能登地方を襲った「令和6年能登半島地震」。この地震発生時に、どこよりも早く現地の医療支援に駆け付けたのが、NPO団体ピースウィンズ・ジャパンが運営する災害医療支援チーム「空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”」である。
その代表を勤めているのが空飛ぶ捜索医療団のプロジェクトリーダーとして20人もの医療、救護、被災地支援のプロを束ねる、医師の稲葉基高。日本海に手を伸ばす半島の指先の珠洲市で、彼らの能登半島地震の支援活動はスタートした。地震発生から1年が経った今、稲葉の目を通してあらためて当時の記憶と記録を振り返るドキュメント連載・第4回――

「緊急の患者を、珠洲市総合病院から金沢大学病院に運びたい。陸路での搬送が厳しいので、ヘリで搬送をしたいのだが、その調整がうまくいってない」
1月4日の早朝、珠洲総合病院に入っているDMATから「保健医療福祉調整本部」にいる稲葉に情報が入った。
この時点で、倒壊家屋から助け出され大ケガをした人など、珠洲市内で緊急を要する患者は珠洲市総合病院に集められていた。珠洲市総合病院は幸いそれほど被災しておらず、非常電源もあり、タンクにも水が貯蔵されている。だが、病院はすでにパンク状態だった。
「病院は相当、混乱しているのだろう」
珠洲市総合病院の医師は不眠不休で治療にあたり、疲労はピークに達している。水などの資源もいずれ底をつく。重症の患者は一刻も早く被災地の外に出す必要があった。
陸路でも透析の患者を救急車で金沢に搬送したが、地震でできたアスファルトの裂け目でタイヤがパンクし引き返すというハプニングも起きていた。
そこでドクターヘリ、自衛隊のヘリを使って患者を搬送しようとしているのだが、その調整がうまくいっていないようだ。
ドクターヘリ(ドクヘリ)は、患者搬送を専門とするヘリコプターだ。石川県にあるドクヘリは石川県立病院を拠点とした1機のみで、今回は中部地方の他県から合計11機のドクヘリが能登半島に駆け付けていた。しかし、それだけではまったく足りていない。1回の搬送でヘリに乗せられる患者の数は原則1名だからだ。
「ウチ(空飛ぶ捜索医療団)のヘリが2機、珠洲市に入っています。共同で搬送しましょうか」
稲葉はすぐさま提案をした。稲葉は患者の調整を行うため、看護師とともに珠洲市総合病院に向かった。
ヘリは被災地では、希少資源である。このような緊急時は、少ないリソースを効率よく運用するため、官民が垣根を越えて協力することが理想だ。
しかし、これまでの被災地では、官民が連携して患者の搬送を行った例はほぼなかった。たとえば、2018年7月の西日本豪雨では、官民の支援チームがそれぞれがバラバラに動いている。
このとき、稲葉たちピースウィンズ(当時はまだ「空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”」が組織されていなかった)は、岡山大学の医師からの要請で、水害で孤立した岡山県倉敷市のまび記念病院に入っていた。

病院は豪雨で1階が水没し、院内の電源が完全に落ちた状態。稲葉たちが水陸両用車で到着したときには、クーラーの利かない病院で一夜を過ごした寝たきりの入院患者などを、一刻も早く病院外に搬送しなければならないという局面にあった。
そこで稲葉が、収容人数の多い自衛隊のボートに搬送を頼んだところ「患者搬送の任務は受けていないから、すぐにできない」と断られてしまったのだ。緊急時とはいえ、“官”は現場の判断で柔軟に動けないという現実に直面した。
結局、ピースウィンズのヘリ2機で8名の患者のピストン搬送を開始。自衛隊のボートは時間をおいて、後から搬送に加わる形になった。この日の搬送は、夜までかかった。
「“官”はリスクを避けるために慎重に動くし、空飛ぶ捜索医療団のような“民”は素早く好き勝手に動こうとする。お互いのカルチャーを理解し、両者が歩み寄らなければ、被災地支援はプラスに働かない」
このときに稲葉が得た教訓だった。
その後、稲葉たち空飛ぶ捜索医療団は、“官”との信頼を深めるため、内閣府・厚労省DMATなどが実施する航空調整の訓練に積極的に参加してきた。こうした訓練を通じて、ドクタ―ヘリや日本赤十字の医師とも顔見知りになり、空飛ぶ捜索医療団の機動性を認知してもらう機会も得た。
またとても細かいことだが、空飛ぶ捜索医療団ではメンバーの茶髪を禁止している。
「被災地に入る際は、空飛ぶ捜索医療団の制服を着用し、身だしなみはしっかり整える」
これは、空飛ぶ捜索医療団の規定で決まっている。なぜ身だしなみを整える必要があるのか。それは、警察や消防や自衛隊に、茶髪の人を見かけないからである。
「警察や消防や自衛隊と連携するには、今の時点では“民”が“官”のカルチャーに寄せていく努力が必要だ。『行政に任せていたら遅れる、だから自分たちNGOが勝手にやればいい』という考えでは、結果的に被災地のためにならない」
緊急時に連携するには、平時のあり方が問われるのだ。
稲葉たちが珠洲市総合病院へ出向くと、そこにいたのはこれまでの災害訓練で顔見知りになっていた、DMATのメンバーだった。稲葉はすぐに、あうんの呼吸が生まれるのを感じた。
「一番緊急の患者1名は医師とともにドクターヘリで、あとの2名は看護師が付き添って空飛ぶ捜索医療団のヘリで搬送しましょう」
どの患者を優先してヘリで搬送するか「トリアージ(治療や搬送の優先度を決めること)」もスムーズにいった。もしこの連携がなかったら、優先度の最も高い人のみが搬送されるという、残酷なトリアージが行われただろう。
空飛ぶ捜索医療団のヘリは、がれきのなかから救出されケガをしている患者と、重症のやけどの患者、計2名を受け持つことになった。
「今までできなかったことが実現した。大きな進歩だ」
ヘリポートになっている中学校へと出発する救急車を見送りながら、稲葉は少し胸を撫で下ろした。
この連携が成功した結果、空飛ぶ捜索医療団は翌日、石川県から直接「5名の中等
症患者をヘリで搬送して欲しい」と要請を受けたのだ。県が直接、民間のNGOに患者の搬送を依頼すること自体、これまでにない連携だった。
こうしてドクヘリ、自衛隊、空飛ぶ捜索医療団の共同搬送は、翌日以降も実施されたのである。

「あぁ、みなさぁーん、おつかれさまですぅ」
翌1月6日、稲葉たちが組織した「保健医療福祉調整本部」に強力な助っ人が入った。被災地医療支援の調整に長けた、DMAT事務局に所属する小早川義貴医師が、珠洲市に駆け付けてくれたのだ。稲葉とも、数々の被災地や訓練で協働してきた人物だった。
小早川医師は、のんびりした声で話すタイプ。彼はどんな緊迫した現場にもスーッと溶け込み、大きな声を出さなくても状況を一つにまとめてしまう不思議な力があった。
いくら決断が必要な場面とはいえ、オラオラした人が調整役になると、DMATはDMAT、赤十字は赤十字と、それぞれがバラバラになって連携がとれなくなってしまうこともある。しかし小早川医師は、どんなシーンでもいつもニコニコしていた。
やさしい雰囲気をまといながら、伝えるべきことはビシッと伝える小早川医師に、稲葉は調整役をバトンタッチした。
その小早川医師へ稲葉が引継ぎをしているときだった。倒壊家屋の捜索をしている現場の消防から、調整本部に連絡が入った。
「倒壊家屋で生命反応がありました。120時間以上も閉じ込められているので、クラッシュシンドロームの兆候がある。医療チームを派遣してほしい」
すでに地震発生から5日が経過し、生存者発見のタイムリミットである72時間はとっくに過ぎている。そんなときに倒壊した家屋で、生存者が発見されたのだ。(第3話へ|第5話につづく)
取材・文=若月 澪子
空飛ぶ捜索医療団”ARROWS” HP:https://arrows.peace-winds.org/
Twitter:https://twitter.com/ARROWS36899898
Facebook:https://www.facebook.com/ARROWS2019
Instagram:https://www.instagram.com/arrows.red2019/
空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”「能登半島地震 緊急支援」の活動記録は以下からご覧いただけます。
WRITER
ライター:
若月 澪子
フリーライター 1975年生まれ。NHKで契約のキャスター、ディレクターとしてローカル放送の制作にあたる。結婚退職後に家事と育児のかたわら、借金苦、就活、中高年の副業に関する取材・執筆を行う。著書に『副業おじさん 傷だらけの俺たちに明日はあるか』(朝日新聞出版)
SUPPORT
ご支援のお願い
支援が必要な人々のために
できること
私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。
一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。