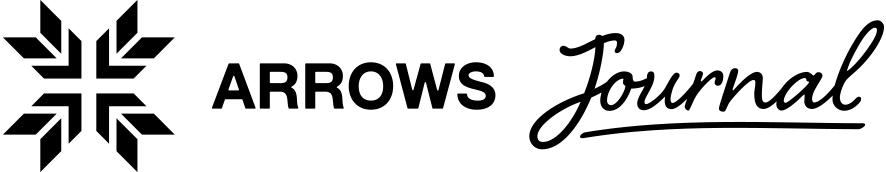
JOURNAL #3972025.01.16更新日:2025.02.13
ライター:若月 澪子

2024年元日に奥能登地方を襲った「令和6年能登半島地震」。この地震発生時に、どこよりも早く現地の医療支援に駆け付けたのが、NPO団体ピースウィンズ・ジャパンが運営する災害医療支援チーム「空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”」である。
その代表を勤めているのが空飛ぶ捜索医療団のプロジェクトリーダーとして20人もの医療、救護、被災地支援のプロを束ねる、医師の稲葉基高。日本海に手を伸ばす半島の指先の珠洲市で、彼らの能登半島地震の支援活動はスタートした。地震発生から1年が経った今、稲葉の目を通してあらためて当時の記憶と記録を振り返るドキュメント連載・第5回――

阪神・淡路大震災(1995年)や四川大地震(2008年)では、クラッシュシンドロームによっても多くの人が命を落としている。クラッシュシンドロームとは、地震で家屋や家具で長時間体を挟まれた状態で突然救出されると、圧迫された部分に溜まった毒素が体中に回り、救出後にショック死してしまう危険がある症状だ。
2024年1月6日の16時過ぎ。石川県珠洲市の保健医療調整本部に、消防から連絡が入った。
「倒壊家屋の下で生命反応のある要救助者が見つかった。すでに120時間以上も閉じ込められていて、クラッシュシンドロームの疑いがある。医療チームを派遣してほしい」
捜索にあたっていた警察が見つけ、消防隊が救助に加わっているようだ。発見されたのは90代の女性だという。
すでに地震発生から6日。緊急消防援助隊は18都府県から2,000人規模、自衛隊は2,000人規模の隊員が石川県に応援に入っていたが、「人命救助のタイムリミット」と言われる72時間はとっくに過ぎている。もはや救助するには絶望的な時期にさしかかっていた。
そんな中での生存者発見の知らせは、支援者たちを湧き立たせた。珠洲市に入ってから倒壊した家屋の救助現場ですでに数名の「死亡宣告」にあたっていた稲葉も、この知らせには喜びと同時に緊張が走った。
「クラッシュシンドロームか……」
クラッシュシンドロームの人を救助するには、「CSM(コンファインド・スペース・メディスン)」という特別な救助医療技術が必要だった。救助隊が体を圧迫する原因になっている梁などを除去する前に医療者が点滴や薬剤を投与し、クラッシュ症候群で最も恐ろしい救助直後の突然死や、その後の腎不全などを予防する処置だ。
災害現場でクラッシュシンドロームの救助経験がある医師は、日本にも数えるほどしかいない。これまで稲葉自身も実際の救助に立ち会ったことはなかったが、派遣要請のあった珠洲の医療本部にいた医師の中で、CSMの訓練を経験しているのは稲葉だけだった。

「医療チームが到着しましたー!」
CSMに必要な点滴や薬剤が本部になかったため、避難所を巡回していたチームに調達するように指示すると、稲葉は看護師1名を連れて現場に急行した。90代の女性が埋まっているという家屋は、すでに多くの警察や消防の人たちに取り囲まれ、テンションが異常に高まっている。稲葉と看護師は、屋根や梁が折り重なる傾いた家の中をまたいで、倒れた柱や壁の中に埋もれた女性のところへ這っていった。
「お母さん、わかりますか?」
意識を確認するために呼びかけたが反応はない。細い隙間から手が見えたので、「手を握って!!」と呼びかけると、わずかな力で弱く握り返してきた。90代の女性にはまだ生命の炎が灯っている。稲葉と看護師は足場が悪い中で、消防隊から輸液を借りて処置を開始した。
これまで空飛ぶ捜索医療団では、年に1度はCSMの訓練を実施している。こうした訓練では、実際に瓦礫を再現した狭い空間で、粉塵用のマスクやゴーグルを付けて行う。稲葉は体の動きが制限された中での処置がいかにやりにくいかを、訓練を通じて味わっていた。
ただし、当然ながら実際の処置はその訓練より何倍も難易度が高い。倒壊した家屋の中では、二次被害に巻き込まれる危険とも背中合わせだ。
稲葉の指示で看護師が女性の左手から点滴を取ろうとするが、2回失敗した。90代の女性の皮膚は、長時間閉じ込められていた影響で激しい脱水と低体温になり、血管が見当たらないのだ。稲葉も首の血管に点滴を指したが、その手は震えていた。
「本当に処置できるだろうか。もしできなかったら……」
日頃、命の瀬戸際に立ち向かう救急医の稲葉でも、こんなに緊張することはない。消防隊員がお湯を入れたビニール袋を用意してくれたので、冷たくなった女性の体を温めた。看護師も左手の点滴を成功させた。
その後、DMATから調達した薬剤が届けられたので、投与を開始する。警察、消防、そして医療チーム、今日初めてここで出会った者同士が、その瞬間のために力を合わせているのだ。

「おばあちゃん頑張れ!」
「もう少しだ!」
外はすでに日が落ちていたが、消防がまぶしいくらい照明をたいていた。現場に降りしきる冷たい雨は、いつの間にか雪に変わっている。それでも女性を励ます150人もの警察官と消防隊員の声は現場を熱くした。
最終的に女性が家から出されたのは20時半ごろ。救出された女性は、担架に乗せられてはじめて、問いかけに対し自分の名前をつぶやいた。
「124時間経過した倒壊家屋からの、奇跡の救出劇」
この出来事は、新聞やテレビなどでも大々的に報道され、一躍「空飛ぶ捜索医療団の稲葉」が注目を集めるきっかけにもなった。しかし、能登半島に生きる人たちの生命力に心打たれていたのは、稲葉のほうだったのだ。
能登半島は、いつもどんよりと曇っている。時折パラパラと雨が降り、雪となる。それでいて、急に雲のすき間から青空が顔を見せ、海に大きな美しい虹がかかることもある。
“奇跡の救助”が行われた半日前のことだった。

「今すぐに向かわないと、また天気が変わる。行くなら今ヘリを飛ばさないと」
コロコロと変わる天候に振り回されながら、稲葉たち空飛ぶ捜索医療団はヘリコプターで孤立集落へと向かっていた。珠洲市内は土砂崩れで道路が寸断され、車では近づくことのできない孤立集落が点在していた。
「孤立集落が多数あり、学校や公民館などに避難所ができているらしい」
不確かな情報が入るものの、何人が避難しているのか、どんな状況にあるのかまったくわからない。ネットも電話も通じないため、状況を確かめるには集落を一つずつ訪れる以外に方法はなかった。空飛ぶ捜索医療団は、自衛隊と協力して孤立集落を巡回することになった。
「地震発生からすでに6日経っている。水道も電気も止まり、燃料も枯渇しているだろう。もし集落の人が全員亡くなっていたら……」
最悪の状況を想定して向かったのは、珠洲市馬緤(まつなぎ)という日本海に面した地区。しかし、ヘリコプターで降り立ってすぐに具合の悪い人たちの診察を開始した稲葉は、この集落の人たちの避難生活に驚かされた。

馬緤の人たちは、190人あまりが小学校など公共施設に6カ所に分かれて避難をしていた。いずれも避難者の半分以上が高齢者だったが、想像していたような悲惨な状況はない。彼らの多くはお互いの顔と名前と居場所を把握していて、この状況を力を合わせ乗り越えているようだった。
「コロナやインフルなどの感染症が流行する時期だから、あまり密集しないほうが……」
避難所の中で数の限られた石油ストーブをぐるりと囲み、寄り添って暖を取る高齢者を見て、稲葉はそうアドバイスすることをためらうほどだった。
さらに、ある集落では、水が出なければ山水を汲んで飲み、食料が足りなければ海からアワビやサザエを採って食べていた。
「田舎ならではだ。都会ではありえない」
稲葉が99歳の老媼がいるという集落まで往診に行ったところ、彼女は七輪にあたりながら、稲葉たちをねぎらってくれた。
「気の毒な……、何か食べていきな」
彼女は被災した自分のことより、はるばるやってきた支援者の身を案じている。稲葉は何かが蘇るような感覚を覚えた。
現代人がさまざまなテクノロジーを駆使する一方で、個人の孤立化・無縁化は急速に進んでいる。でも、この土地の人たちの営みは変わらない。ここでは、地域のネットワークや自然そのものが生活インフラなのだ。
災害に苦しめられてきた土地に生きているからこそ、助け合いが必要ということが骨身にしみているのだろう。稲葉はここに来て、能登の人のたくましさに自分のほうが癒され、そして力を与えられる気がしていた。(第4話へ|第6話につづく)
取材・文=若月 澪子
空飛ぶ捜索医療団”ARROWS” HP:https://arrows.peace-winds.org/
Twitter:https://twitter.com/ARROWS36899898
Facebook:https://www.facebook.com/ARROWS2019
Instagram:https://www.instagram.com/arrows.red2019/
空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”「能登半島地震 緊急支援」の活動記録は以下からご覧いただけます。
WRITER
ライター:
若月 澪子
フリーライター 1975年生まれ。NHKで契約のキャスター、ディレクターとしてローカル放送の制作にあたる。結婚退職後に家事と育児のかたわら、借金苦、就活、中高年の副業に関する取材・執筆を行う。著書に『副業おじさん 傷だらけの俺たちに明日はあるか』(朝日新聞出版)
SUPPORT
ご支援のお願い
支援が必要な人々のために
できること
私たちの活動は、全国のみなさまのご支援・ご寄付によって支えられています。
一秒でも早く、一人でも多くの被災者を助けるために、空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”へのご寄付をお願いいたします。